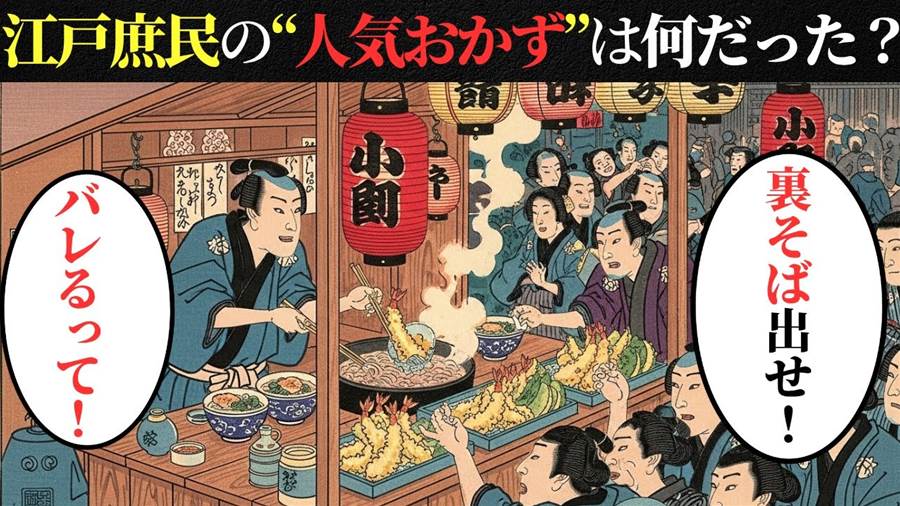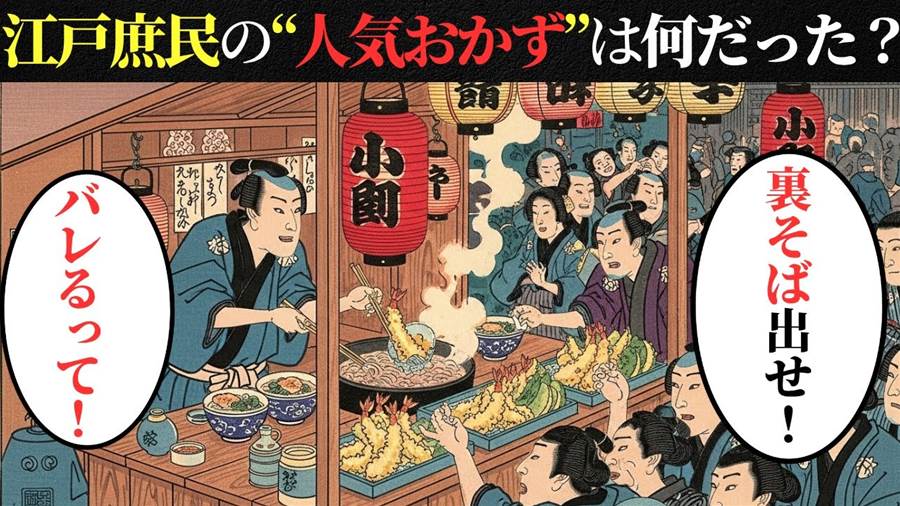江戸の夕暮れ、狭い長屋の屋根が赤く染まり、行商人の声と味噌汁の香りが漂う中、若い大工の憲二は冷や飯を食べながら一日の終わりを迎えていた。「今日は外でたまには贅沢にしないか?」と友人に誘われるが、憲二はいつもの夕飯で我慢する。しかし、江戸の食生活は変わりつつあった。長い労働に耐える職人たちは次第に食事の回数を増やし、毎朝の温かい味噌汁と漬物が彼らの活力の源となっていた。ある日、憲二は体の不調に気づき始める。「何か最近足がだるいな」とつぶやくも、忙しさにかまけて食事の改善には至らなかった。しかし、屋台の蕎麦や天ぷらの香りが彼の興味を引き、外食文化は彼の日常に小さな変化をもたらす。ある日、疲れた憲二の元に豆腐屋の娘が丁寧に包んだ豆腐を届けにくる。「これを食べて元気になって」とその温かい言葉に、憲二の心は癒された。江戸の食文化と人との温かいつながりは、厳しい暮らしの中で彼を支える光となった。